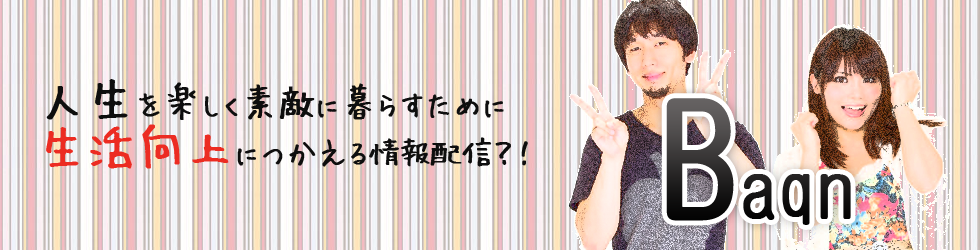土用の丑の日にうなぎを食べるようになったなぜ?うなぎを食べるとどんな効果が得られるの?
土用の丑の日といえば、うなぎを食べる日という事で知られていますが、土用の丑の日が一体なんの日なのか知らないという人は多いと思います。
どういった意味か知らないけど、土用の丑に日にはうなぎを食べていた人は、土用の丑に日がどういった日なのか知りたくはありませんか?
土用の丑の意味とうなぎが食べるようになった理由を調べてみましたよ!
〇土用の丑の日って一体なんなのか?
まず、土用の丑の日での「土用」というのは、立春、立夏、立秋、立冬と言われる季節の始まりの前日から17~19日前の期間のことを指しています。
土用の期間は、地球の軌道によって変化するため毎年日数が変わり、1年で70日ぐらいが土用の日であるため、土用の日は実は珍しくありません。
そして、丑の日は干支から来ており、干支といえば年のイメージが強いですが、日付にも干支が割り振られており、12日に1回丑の日がやってきます。
土用の丑の日というのは、土用と言われる期間の丑の日のことを指していますが、土用は1年で約70日もありますので、土用の丑の日は1年で約6回も発生します。
しかし、私たちが土用の丑の日と言った場合は、夏の土用の丑の日になります。
ちなみに、夏の土用は18~19日ありますので、50%以上の確率で夏の土用の丑の日は1年に2回あり、2回目を「二の丑」といいます。
土用の丑の日の意味はわかったと思いますが、なぜ夏の土用の丑の日にうなぎを食べるようになったでしょうか?
〇土用の丑の日にうなぎを食べるのはなぜ?
土用の丑の日にうなぎを食べるようになったのは諸説ありますが、最もよく言われているのは、旬を過ぎて売れないうなぎを売るために土用の丑の日にうなぎを食べると夏に負けないと言って売り出したのがはじまりとされています。
また、丑の日に「う」と名前が付いている食べ物を食べると夏に負けにくくなる風習があったという
このように、土用の丑の日はうなぎを食べると良いと売り出した所、売り上げが上がったため、他のお店も真似をして土用の丑の日はウナギの日と売り始め、日本に広まったとされています。
この話から分かるように、実はうなぎの旬は夏ではなく冬であり、冬のうなぎは脂がのっておいしいのです。
日本の風習なので夏に食べるのも良いですが、おいしいウナギを食べたい人は、冬にうなぎを食べる事もおすすめです。
個人的な話にはなりますが、高いウナギを食べるならおいしい時期に食べたいので、いつも夏の土用の丑の日は無視して、冬にうなぎを食べるようにしています。
〇うなぎは夏バテを防止してくれる作用はあるの?
土用の丑に日にうなぎを食べる理由の一つは、夏バテを防止するためだと思います。
うなぎには、ビタミンAやビタミンBといった栄養素が豊富に含まれ、脂肪が多くカロリーが高いためエネルギー不足を解消してくれる効果があります。
ただし、現在の日本は食品があふれている時代であり、栄養素が不足したり、カロリー不足したりする事は少ないため、うなぎが夏バテの予防の効果は薄いとされています。
逆に、暑くなって胃腸が弱っている時に、ウナギを食べると下痢などを起こし、より胃腸の調子が悪くなることも注意が必要だとされています。
食欲が低下してしまう夏に、うなぎで食欲がそそられるのは良い事ですが、すでに胃腸の調子が悪い場合は、負担となってしまうこともありますので、止めておくことをおすすめします。
うなぎを食べるよりも野菜や発酵食品などを食べて、胃腸の調子を整えるようにした方が夏バテの防止になるかもしれません。
うなぎは冬に食べた方がおいしいですし、夏バテを予防する効果も弱くなっているかもしれませんが、日本の風習ですので、夏にうなぎを食べて見てはどうでしょうか?